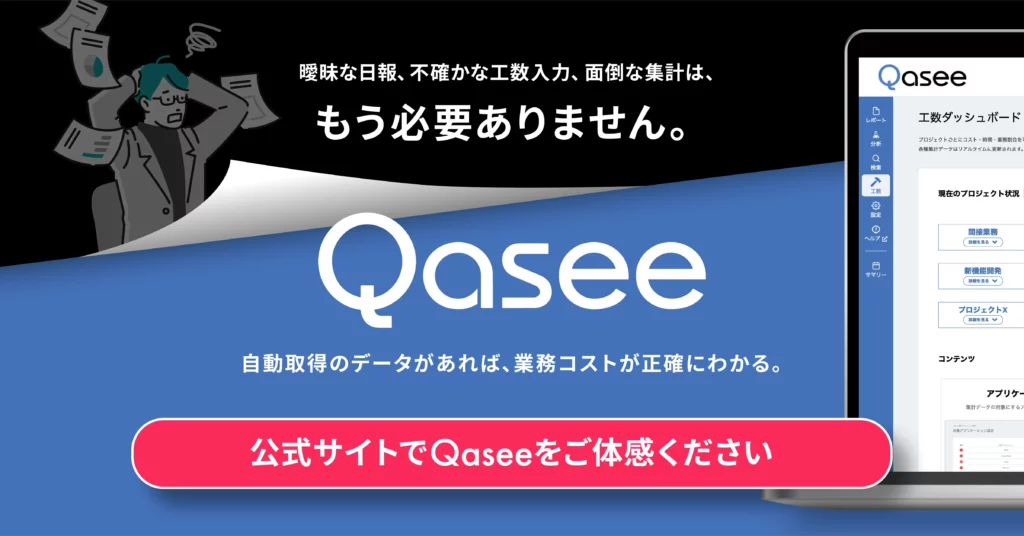工数管理ツールおすすめ16選|選び方と導入メリットを徹底解説

「Excelで工数を管理しているけど、もう限界かも……」
そんな悩みを抱えていませんか?
工数管理は、チームの生産性を上げ、正確な原価やリソース配分を把握するために欠かせない業務です。しかし現場では、「入力が面倒で続かない」「集計に時間がかかる」「結局、データがバラバラで分析できない」といった課題に直面するケースが少なくありません。
こうした課題を解決する手段として注目されているのが、工数管理ツールです。ツールを導入すれば、作業時間の自動記録や進捗のリアルタイム把握、レポート作成の自動化までを実現でき、これまで“手間”だった工数管理を“仕組み”として運用できるようになります。
本記事では、
✅ 工数管理ツールの選び方と比較ポイント
✅ 最新のおすすめ16選(2025年最新版)
✅ 導入で得られる具体的なメリット
✅ 自動化によって入力ゼロを実現する「Qasee」
を徹底解説します。
「どのツールを選べばいいかわからない」
「Excel管理を卒業して効率化したい」
そんな方に向けた記事となっています。
~目次~
・工数管理ツール比較のポイント
・工数管理ツールおすすめ16選【2025年最新版】
・工数管理ツールとは?目的と導入が進む背景
・工数管理ツールを導入する5つのメリット
・工数管理ツールの選び方|失敗しないチェックポイント
・導入事例から見る、工数管理ツール活用の成功ポイント
・Qaseeが実現する“自動化された工数管理”
・まとめ|工数管理ツールは“継続できる仕組み”で選ぶ
工数管理ツール比較のポイント
工数管理ツールには、自動でログを取得するタイプから手動入力型まで、さまざまな種類があります。
機能や費用、運用のしやすさも大きく異なるため、「有名だから」「無料だから」といった理由だけで選ぶと、現場に定着しないこともあります。
ここでは、ツールを選ぶ前に押さえておきたい5つの比較ポイントを紹介します。それぞれの特徴を理解しておくことで、自社に最適なツールを見極めることができます。
自動計測型 or 手動入力型かを確認する
工数管理ツールは大きく分けて、**「自動計測型」と「手動入力型」**の2種類があります。どちらにもメリットと注意点があり、業務スタイルや管理目的によって適したタイプが異なります。
◾️自動計測型ツール
PCの操作ログやアプリ利用履歴を自動で収集し、誰が・いつ・どの業務に・どれだけの時間を使ったかを自動で算出するタイプです。 従業員の入力負担をほぼゼロにでき、データの正確性・継続性が高いのが特徴です。
- メリット:入力忘れや記録ミスを防げる/リアルタイムで稼働状況を把握できる
- 向いている企業:IT企業・クリエイティブ職・開発チームなど、PC作業が中心の組織
代表的な自動計測型ツールのひとつが、**Qasee(カシー)**です。PC上の操作ログをもとに作業内容を自動で可視化できるため、入力作業をほとんど必要とせず、正確で継続性のあるデータ取得を実現します。
こうした仕組みにより、従来の工数管理で課題となっていた「入力負担」や「記録のばらつき」を解消できるのが特徴です。
◾️手動入力型ツール
作業ごとに自分で工数を入力するタイプで、プロジェクト単位やタスク単位の管理に適しています。Excelやスプレッドシートを使っている企業が、まず取り入れやすい形式でもあります。
- メリット:細かいタスク単位で記録できる/現場主導の柔軟な運用が可能
- 向いている企業:小規模チームやアナログ管理から移行したい企業
ただし、入力の手間や記録漏れが発生しやすいため、運用ルールの徹底が重要です。最初は手動入力型から始め、運用が定着してきた段階で自動化ツールに移行する企業も増えています。
目的の違いによって比較する
工数管理ツールにはさまざまなタイプがありますが、大きく分けると「プロジェクト管理対応型」「工数管理特化型」「勤怠管理システム搭載型」の3種類に分類できます。自社の課題や運用体制に合わせて、最適なタイプを選ぶことが重要です。
・プロジェクト管理対応型:ガントチャートで進捗と工数を一元管理
BacklogやJootoなどに代表されるタイプで、プロジェクト進行を「見える化」しながら工数も同時に管理できるのが特徴です。ガントチャートを使ってタスクの進捗と担当者の稼働状況を確認でき、スケジュール遅延やリソースの偏りを早期に発見できます。
どちらかといえば「プロジェクト全体の動きを管理したい」マネージャー視点に強いツールで、進捗・タスク・工数をまとめて管理したい企業に向いています。
・工数管理特化型:作業実態を可視化し、生産性の改善に直結
Qaseeのように、実際の作業ログをもとに稼働データを自動収集・分析できるタイプです。
単なるタスク単位の記録ではなく、「どんなアプリをどれだけ使っていたか」「集中時間がどのくらいあったか」など、より実態に近い工数を高精度に把握できます。
このタイプは、日報や報告の手間を減らすだけでなく、チームや個人の働き方をデータで改善することを目的としています。
プロジェクト管理対応型が「スケジュールと進捗の見える化」なのに対し、工数管理特化型は「時間の使い方そのものの見える化」に強みがあります。
・勤怠管理システム搭載型:出退勤と工数をまとめて管理
ジョブカン勤怠管理やTeamSpiritなどに代表されるタイプで、勤怠データと工数を一元管理できるのが特徴です。
出退勤の打刻データをもとに、各メンバーの稼働時間を集計できるため、**勤務時間の把握や残業管理、法令遵守(労働基準法対応)**に強みがあります。
また、出退勤データとプロジェクト別工数を紐づけることで、**「働いた時間」と「どの業務に費やしたか」**を同時に可視化できます。
工数を管理しながら、社員の労働時間や勤務実態を正確に記録できるため、コンプライアンス強化・労務リスク対策・働き方改革の推進にも直結します。
このタイプは、プロジェクト管理対応型や工数管理特化型に比べて、経理・人事部門やバックオフィス主導の運用に向いており、特に「勤怠・労務と工数をまとめて管理したい中堅企業〜大企業」での導入が増えています。
導入規模とコスト感を比較する
工数管理ツールは、チームの規模と導入目的によってコストが大きく変わります。小規模チーム向けのツールは、1ユーザーあたり月500〜1,000円程度が一般的。クラウドログやTimeCrowdなど、手軽に始められるクラウド型が多く、導入ハードルが低いのが特徴です。
一方、中〜大規模向けツールは、ERPや勤怠システムとの連携機能を備え、1ユーザーあたり2,000円前後が相場。TeamSpiritやZACのように、会計・人事・工数を統合管理できるタイプが代表的です。
また、Qaseeのように自動計測で入力負荷を減らすタイプは、導入負担が少なく、長期的な運用コストを抑えやすいのが強みです。
比較の際は、「価格の安さ」だけでなく、
- 管理の手間をどれだけ減らせるか
- 自動化による人件費削減効果
といったトータルコストの視点で判断するのがポイントです。
他ツールとの連携性
工数管理ツールを選ぶうえで、他の業務ツールとどれだけ連携できるかは非常に重要なポイントです。単体で使うよりも、既存のシステムとデータをつなげることで、業務全体の効率が大きく向上します。
たとえば、**プロジェクト管理ツール(Backlog・Asana・Jootoなど)**と連携すれば、タスクの進捗と実際の工数を自動で突き合わせることができます。また、**勤怠管理や会計システム(ジョブカン・freee・ZACなど)**と連携すれば、稼働データをもとに原価や人件費を自動計算することも可能です。
さらに、最近ではBIツール(Tableau・Looker Studioなど)と接続して、工数データを経営指標と紐づけて分析できるタイプも増えています。
こうした連携機能を活用すれば、「現場の見える化」から「経営判断の自動化」までを一気通貫で実現できます。
ツールを比較する際は、
- どのシステムと連携できるか(プロジェクト/勤怠/会計)
- API連携やCSV出力など、データ活用の自由度
を確認しておくと、導入後の運用がスムーズになります。
データの活用レベル(ダッシュボード・レポート機能)
工数管理ツールは、データを「記録するだけ」ではなく、どう活用できるかが重要です。ダッシュボード機能があるツールなら、プロジェクト別・個人別の稼働状況をリアルタイムで可視化できます。
また、レポート機能が充実していれば、集計や報告資料を自動生成でき、分析作業の手間を大幅に削減できます。特に自動計測型のツールでは、日々の作業ログがそのまま分析データとなり、入力なしで最新の稼働状況を把握できます。
これにより、管理者・経営層・現場が同じ情報を共有しながら改善を進めることが可能になります。
比較時は、
- 見やすいダッシュボードの有無
- レポート自動化の範囲
- 部門間での共有しやすさ
を確認しておくと、導入後の効果を最大化できます。
工数管理ツールおすすめ16選【2025年最新版】
市場には、プロジェクト管理・勤怠管理・原価管理など、さまざまな機能を持つ工数管理ツールが登場しています。しかし「どれを選べばいいかわからない」「自社に合うツールが見つからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
ここでは、目的別に選びやすいおすすめの工数管理ツール16選を紹介します。自動で工数を可視化できるツールから、プロジェクト単位で詳細に管理できるタイプまで、特徴や強みを比較しながら解説します。
Qasee(カシー)|PC作業の自動可視化で入力ゼロを実現

Qasee(カシー)は、PC上の作業ログを自動で収集し、**「誰が・いつ・どの業務に・どれだけの時間を使ったのか」**を正確に可視化できる工数管理ツールです。
従業員が手動で入力する必要がなく、操作履歴をもとに自動で工数を算出。入力ミスや記録漏れを防ぎながら、リアルタイムで精度の高いデータを蓄積します。
また、チーム・プロジェクト単位で稼働状況を分析できるため、リソース配分の最適化や生産性向上の指標づくりにも最適。
「入力の手間をなくし、正確なデータで改善を回したい」企業におすすめのツールです。
| 運営会社 | Qasee 株式会社 |
| 公式サイト | https://qasee.jp/task/ |
| 初期費用 | 要問い合わせ |
| 料金プラン | 要問い合わせ |
| 工数入力方法 | 自動取得 |
クラウドログ(CrowdLog)

クラウドログ(CrowdLog)は、案件単位・タスク単位で工数を簡単に記録できるクラウド型ツールです。タイマー計測と手動入力の両方に対応しており、現場のスタイルに合わせた柔軟な運用が可能です。ブラウザ上で「誰が・どのプロジェクトに・何時間使ったか」をリアルタイムで可視化できます。
また、ガントチャートや原価管理、レポート機能も搭載。部門別・期間別・クライアント別など多様な集計が行え、工数の見える化からコスト管理までを一元化できます。
シンプルな操作性と管理機能を両立した、汎用性の高い工数管理ツールです。
| 運営会社 | 株式会社クラウドワークス |
| 公式サイト | https://www.crowdlog.jp/ |
| 初期費用 | 要問い合わせ |
| 料金プラン | ・無料トライアル ・ベーシックプラン ・プレミアムプラン |
| 工数入力方法 | タイマー計測、手動入力 |
クラウドERP ZAC

クラウドERP ZACは、工数管理・原価計算・売上管理を一元化できるERP型のクラウドツールです。
プロジェクトごとに工数・コスト・利益をリアルタイムで可視化し、経営判断に直結する正確な収支データを提供します。
入力方式は、手動入力に加え、勤怠システムとの連携による自動反映にも対応。現場の記録作業を効率化しながら、会計・請求処理までをシームレスに接続できます。
「工数を管理するだけでなく、原価や利益まで見たい」──そんな企業に最適な、高機能型の工数管理ソリューションです。
| 運営会社 | 株式会社 オロ |
| 公式サイト | https://www.oro.com/zac/ |
| 初期費用 | ZAC初期設定費用(10万円)+導入支援費用 |
| 料金プラン | 要問い合わせ |
| 工数入力方法 | 手動入力 |
Lychee Redmine

Lychee Redmineは、オープンソースの「Redmine」をベースに開発された、プロジェクト管理特化型の工数管理ツールです。
ガントチャートを中心に、タスク・進捗・工数を一元的に可視化でき、開発・制作・コンサルなどのチーム運用に幅広く対応します。
入力は手動形式が基本ですが、タイムトラッキング機能を使えば、作業時間をリアルタイムに計測しながら登録することも可能です。
プロジェクト単位で「誰が・どのタスクに・どれだけ時間を使っているか」を把握でき、スケジュール遅延の早期発見にも役立ちます。また、カスタマイズ性が高く、自社のワークフローや管理指標に合わせて柔軟に運用できる点も魅力です。
| 運営会社 | 株式会社 アジャイルウェア |
| 公式サイト | https://lychee-redmine.jp/ |
| 初期費用 | 0円 |
| 料金プラン | ・フリー:0円(1ユーザー) ・スタンダード:1ユーザー900円/月 ・プレミアム:1ユーザー1,400円/月 ・ビジネス:1ユーザー2,100円/月 |
| 工数入力方法 | 手動入力、タイムトラッキング |
チームスピリット(TeamSpirit)

チームスピリット(TeamSpirit)は、勤怠管理・工数管理・経費精算を一体化した業務管理プラットフォームです。Salesforce上で動作するクラウドサービスとして、多くの大手企業で導入されています。
工数の入力は、勤怠情報と連動した手動登録型。出退勤データをもとに、業務ごとの時間を簡単に記録できるため、勤怠と工数を別々に管理する手間を省けます。
また、リアルタイムで稼働状況や残業時間を可視化できるため、労務コンプライアンスと生産性管理を同時に強化可能。
人事・経理・現場を横断した「働き方の見える化」を実現したい企業に最適なツールです。
| 運営会社 | 株式会社チームスピリット |
| 公式サイト | https://www.teamspirit.com/ |
| 初期費用 | 要問い合わせ |
| 料金プラン | ・TeamSpirit 勤怠:24,000〜/月 ・TeamSpirit 工数:18,000〜/月 ・TeamSpirit 経費:18,000〜/月 |
| 工数入力方法 | 手動入力 |
Asana
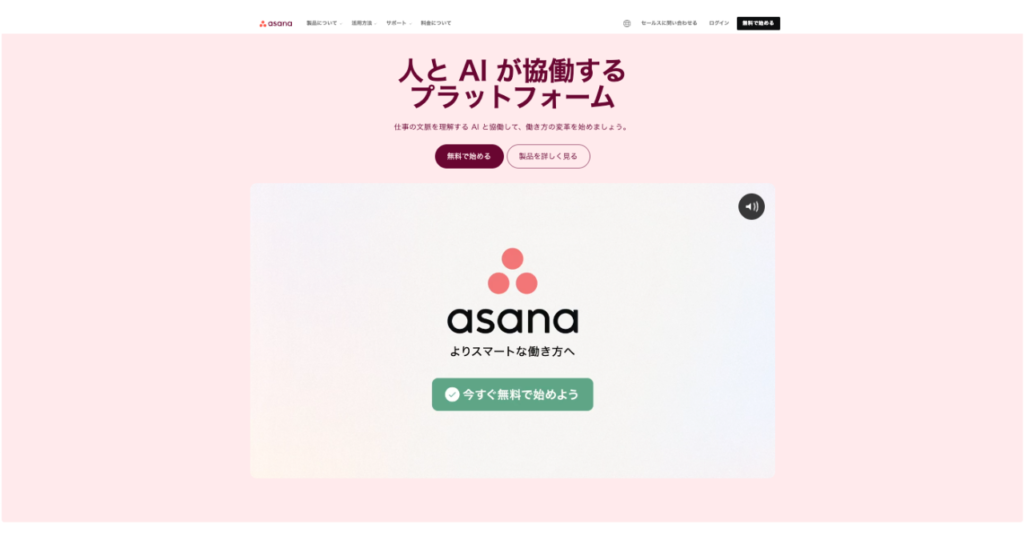
Asanaは、世界190か国以上で利用されるグローバルスタンダードなプロジェクト管理ツールです。タスク単位で進捗を可視化でき、ガントチャート・カレンダー・ボードなど多様なビューでチームの作業状況を把握できます。工数管理は、手動でのタイムトラッキング入力に対応。
有料プランでは「タイムトラッキング」機能を使い、各タスクに実績時間を紐づけて管理できるほか、外部ツール(ClockifyやHarvestなど)と連携することで自動計測も可能です。
シンプルな操作性と豊富な連携機能により、小規模チームから大企業まで柔軟に対応できる汎用型ツールとして人気を集めています。
| 運営会社 | Asana, Inc. |
| 公式サイト | https://asana.com/ja |
| 初期費用 | 要問い合わせ |
| 料金プラン | ・Personal:無料 ・Starter:1ユーザー1,200円/月 ・Advanced:1ユーザー2,700円/月 ・Enterprise:要問い合わせ |
| 工数入力方法 | 手動タイムトラッキング |
TimeCrowd

TimeCrowdは、チーム全体の作業時間をリアルタイムに可視化できるタイムトラッキングツールです。
ブラウザやアプリ上でワンクリック計測が可能で、**「誰が・何の作業を・いつ・どれくらい行っているか」**をシンプルに記録できます。
入力方式は半自動型。メンバーが作業開始・終了をクリックするだけで時間が記録され、タスク名やプロジェクトを指定しておけば集計も自動化されます。
そのため、スプレッドシートのような手入力管理に比べて、記録漏れやミスを大幅に削減できます。
「チームの時間の使い方を透明化したい」「働き方の改善に活かしたい」企業に最適な、軽量かつ実用的な工数管理ツールです。
| 運営会社 | タイムクラウド株式会社 |
| 公式サイト | https://timecrowd.net/ |
| 初期費用 | 要問い合わせ |
| 料金プラン | 要問い合わせ |
| 工数入力方法 | 半自動(作業開始と終了のタイミングでクリック) |
Jooto

Jootoは、シンプルな操作性と視覚的なタスク管理が特徴のクラウド型プロジェクト管理ツールです。カンバン方式で「誰が・どのタスクを・いつまでに」進めているかをひと目で把握でき、進捗管理がスムーズに行えます。
工数管理は、手動入力型のタイムトラッキング機能を備えています。各タスクごとに実績時間を記録し、担当者別・案件別の作業時間を集計可能。他の勤怠管理ツールやスプレッドシートと連携すれば、より正確な稼働データを取得できます。
中小企業やチーム単位のプロジェクト運用に適しており、**「まずはタスク管理から工数管理を始めたい」**という企業におすすめのツールです。
| 運営会社 | 株式会社PR TIMES |
| 公式サイト | https://www.jooto.com/ |
| 初期費用 | 要問い合わせ |
| 料金プラン | ・無料:0円(~5ユーザー) ・スタンダード:1ユーザー500円/月 ・ビジネス:1ユーザー1,300円/月 ・タスクDX:要問い合わせ |
| 工数入力方法 | 手動タイムトラッキング |
Brabio!

Brabio!は、ガントチャートを中心としたタスク・工数管理ツールです。プロジェクトごとにタスクを視覚的に整理でき、進捗をドラッグ&ドロップで簡単に更新できます。
工数管理は手動入力型で、各タスクに対して担当者・予定工数・実績工数を記録可能。メンバーごとの稼働量をグラフで確認でき、Excel感覚でプロジェクト全体の工数を俯瞰できます。
中小規模のチームや複数案件を同時進行する企業に最適で、**「ガントチャートで直感的に管理したい」**というニーズに特化した設計が特徴です。
| 運営会社 | ブラビオ株式会社 |
| 公式サイト | https://brabio.jp/ |
| 初期費用 | 要問い合わせ |
| 料金プラン | ・フリー:0円(5ユーザー) ・プラン10:3,300円/月 ・プラン20:6,600円/月 ・プラン30:9,900円/月 ・プラン40:13,200円/月 ・プラン50:16,500円/月 |
| 工数入力方法 | 手動入力 |
freee工数管理

freee工数管理は、会計・人事・勤怠情報と連携できる工数管理ツールです。freee会計・人事労務との統合により、作業時間の記録から人件費の配賦までを一元的に管理できます。
入力方式は手動入力型で、メンバーがプロジェクトやタスクごとに工数を登録するスタイル。ただし、勤怠データと連動するため、出退勤時間から自動的に稼働時間を算出できる仕組みもあります。
これにより、手入力の手間を減らしつつ、実績データの整合性を保てるのが特徴です。会計データと連携して原価計算や予実管理まで一気通貫で行いたい企業に最適なツールです。
| 運営会社 | フリー株式会社 |
| 公式サイト | https://www.freee.co.jp/project-management/ |
| 初期費用 | 0円 |
| 料金プラン | ・管理者ライセンス:1ユーザー/2,400円/月 ・メンバーライセンス:1ユーザー/600円/月 |
| 工数入力方法 | 手動入力 |
Pace

Paceは、プロジェクト単位の進捗管理と工数把握を直感的に行える国産ツールです。ガントチャートによるスケジュール管理と、タスクごとの実績工数記録を一画面で確認でき、シンプルながらも運用しやすい設計が特徴です。
入力方式は手動入力型ですが、UIが分かりやすく、担当者が迷わず実績時間を登録できるようになっています。プロジェクトごとの予定工数と実績を比較できるため、リソース配分や予算超過の兆候を早期に把握可能です。
中小規模のチームや受託開発・制作系の企業に人気があり、**「過剰な機能は不要。必要な範囲で工数を管理したい」**という企業に適したバランス型ツールです。
| 運営会社 | 株式会社リーピー |
| 公式サイト | https://paces.jp/ |
| 初期費用 | 要問い合わせ |
| 料金プラン | 1ユーザー550円/月 |
| 工数入力方法 | 手動入力 |
monday.com

monday.comは、世界的に利用されているプロジェクト・タスク管理プラットフォームで、チームの作業状況や工数を一元的に把握できるのが特徴です。
ガントチャート、カンバン、タイムトラッキング機能などを柔軟に組み合わせて使えるため、業種や業務内容を問わず導入しやすいツールです。
入力方式は手動入力+タイムトラッキング併用型で、タスクごとの作業時間をボタンひとつで計測可能。API連携にも優れており、SlackやGoogle Workspaceなど外部サービスとのデータ連携を自動化できます。
視覚的に整理されたダッシュボードで、**「今どの業務に時間がかかっているか」**を即座に把握できるのが大きな強みです。
| 運営会社 | 株式会社ギャプライズ |
| 公式サイト | https://monday.com/lang/ja |
| 初期費用 | 要問い合わせ |
| 料金プラン | ・Basic:1ユーザー1,300円/月 ・Standard:1ユーザー1,650円/月 ・Pro:1ユーザー3,200円/月 ・Enterprise:要問い合わせ |
| 工数入力方法 | 手動入力、タイムトラッキングの併用 |
ジョブカン勤怠管理

ジョブカン勤怠管理は、出退勤管理と工数把握を同時に行える勤怠管理システムです。打刻データをもとに勤務時間を自動集計し、プロジェクトや業務区分ごとの工数として記録できます。
入力方式は半自動型で、基本的には勤怠データを自動取得しつつ、必要に応じて担当者が業務区分を選択して紐づける形式。
すでにジョブカンシリーズ(経費精算・ワークフローなど)を導入している企業であれば、各システムとの連携により運用を統一できます。
勤怠・工数・労務管理を一元化したい企業に最適で、バックオフィス全体の効率化を図りたい中堅企業以上に特に人気の高いツールです。
| 運営会社 | 株式会社DONUTS |
| 公式サイト | https://jobcan.ne.jp/ |
| 初期費用 | 0円 |
| 料金プラン | 1ユーザー200〜500円/月 ※利用機能数によって変動 |
| 工数入力方法 | 勤怠データを元に業務区分を手動で紐付け |
OBPM Neo

OBPM Neoは、プロジェクト単位の原価管理や収益分析を高精度に行える国産ツールです。工数・経費・売上データを一元管理し、リアルタイムでプロジェクトごとの損益を可視化できるのが特徴です。
入力方式は手動入力型ですが、ガントチャートやタスク管理と連動しており、作業時間を登録しながらプロジェクト進捗を把握できます。
特に、SIer・システム開発・コンサルティングなど、人件費が主要コストとなる業種で導入が進んでいます。
原価計算や利益率分析など、経営管理に踏み込んだ活用ができる点が強みで、「現場の見える化」と「経営数値の精度向上」を両立したい企業に最適です。
| 運営会社 | 株式会社システムインテグレータ |
| 公式サイト | https://products.sint.co.jp/obpm |
| 初期費用 | 要問い合わせ |
| 料金プラン | ・10ライセンス:105,000円/月 ・20ライセンス:157,500円/月 ・30ライセンス:189,000円/月 ・40ライセンス:231,000円/月 ・50ライセンス:262,500円/月 |
| 工数入力方法 | 手動入力 |
Backlog

Backlogは、タスク管理・進捗共有・コミュニケーション機能を一体化した国産のプロジェクト管理ツールです。
ソフトウェア開発やWeb制作など、複数メンバーが関わる業務の進行を「見える化」しながら工数を管理できます。
入力方式は手動入力型で、タスクごとに作業時間を記録可能。ガントチャート・カンバン・バーンダウンチャートなど多彩な可視化機能を備えており、プロジェクト全体の負荷分散や進行状況を把握しやすい構成になっています。
また、GitやSlackなど外部ツールとの連携性にも優れており、開発チームを中心に幅広い業種で活用されています。プロジェクト進行を軸に工数を管理したい企業におすすめです。
| 運営会社 | 株式会社ヌーラボ |
| 公式サイト | https://backlog.com/ja/ |
| 初期費用 | 要問い合わせ |
| 料金プラン | ・フリー:0円(10ユーザー) ・スターター:2,970円/月 ・スタンダード:17,600円/月 ・プレミアム:29,700円/月 ・プラチナ:82,500円/月 |
| 工数入力方法 | 手動入力 |
Redmine

Redmineは、オープンソースのプロジェクト管理ツールとして世界中で利用されている定番システムです。
タスク管理・進捗管理・チケット管理を中心に構築されており、プラグインを追加することで工数管理機能を柔軟に拡張できます。
入力方式は手動入力型で、タスクごとに作業時間を登録する仕組み。
シンプルな構成ながら、ガントチャート・ロードマップ・Wiki機能などを標準搭載しており、開発チームを中心に多くの企業で採用されています。
自社の要件に合わせてカスタマイズしたい、技術リソースを持つ企業や開発組織にとって最適な選択肢といえるでしょう。
| 運営会社 | ファーエンドテクノロジー株式会社 |
| 公式サイト | https://redmine.jp/ |
| 初期費用 | 要問い合わせ |
| 料金プラン | ・My Redmine:11,000円/月 ※ユーザー1000名・PJ無制限 |
| 工数入力方法 | 手動入力 |
工数管理ツールとは?目的と導入が進む背景
工数管理ツールは、業務ごとの作業時間や人員リソースを「見える化」するシステムです。Excelでの集計を自動化し、プロジェクト別や社員別に稼働を可視化できます。
近年は、DX推進や労働時間管理の厳格化を背景に、原価計算や経営判断にも活用できるデータ基盤として導入が広がっています。
工数管理ツールの基本機能と役割
工数管理ツールの主な役割は、業務時間を正確に記録・可視化し、組織全体の生産性を高めることです。基本機能としては、以下のようなものがあります。
作業時間の記録・集計機能
タスクやプロジェクト単位で作業時間を記録し、自動または手動で集計。チームや個人の稼働状況を定量的に把握できます。
プロジェクト別・担当者別の分析機能
どの業務にどれだけ時間が使われているかを可視化し、リソース配分の偏りやボトルネックを発見できます。
レポート・ダッシュボード機能
データをグラフや表で自動的に可視化。管理者はリアルタイムに稼働を確認し、改善施策の判断材料にできます。
コスト・原価管理との連携
人件費をプロジェクト単位で割り出し、原価計算や利益分析に活用することも可能です。
これらの機能を通じて、工数管理ツールは**「見える化」から「改善」へつなげる基盤**として機能します。
導入が加速する理由(DX・人件費高騰・労働時間管理の厳格化)
工数管理ツールの導入が急速に広がっている背景には、3つの大きな社会的要因があります。
DX推進による業務のデジタル化
紙やExcelに依存した管理から脱却し、業務データをリアルタイムで分析できる体制を整える動きが加速しています。ツール導入により、業務効率化だけでなく経営判断のスピードアップも可能になります。
人件費の高騰とリソースの最適化
人件費が上昇する中、どの業務にどれだけ時間をかけるべきかを把握し、ムダをなくすことが求められています。工数管理ツールはそのための「データ基盤」として機能します。
労働時間管理の厳格化(働き方改革関連法への対応)
法令対応としても、正確な労働時間の把握は不可欠です。工数データをもとに残業時間や業務量を可視化することで、コンプライアンス強化にもつながります。
これらの要因が重なり、今や工数管理ツールは「効率化ツール」ではなく、経営・労務・ガバナンスの中核を担うシステムとして位置づけられています。
工数管理ツールを導入する5つのメリット
工数管理ツールを導入することで、単に「作業時間を記録する」だけでなく、業務効率化から経営判断の高度化まで幅広い効果を得ることができます。ここでは、導入によって得られる代表的な5つのメリットを紹介します。
手動入力を減らして精度を高められる
従来のExcelや手動入力による工数管理では、「入力忘れ」「記録のばらつき」「集計ミス」といった課題がつきものでした。
工数管理ツールを導入すれば、PCの操作ログやアプリ利用履歴などから自動で作業時間を取得できるため、記録の精度が飛躍的に向上します。
また、ツールが自動的にデータを蓄積・更新してくれるため、現場の入力負担を大幅に削減できます。
「入力が面倒で続かない」「締め切り前にまとめて記入している」といった運用上の問題を防ぎ、“正確で継続できる”工数管理を実現します。
リアルタイムで進捗・稼働を把握できる
工数管理ツールの大きな強みは、チームや個人の稼働状況をリアルタイムで把握できることです。
ツール上で自動的に集計されたデータがダッシュボードに反映され、誰が・どのプロジェクトに・どれだけの時間を使っているかを瞬時に確認できます。
これにより、進捗の遅れや特定メンバーへの負荷集中を早期に発見でき、リソースの再配分やスケジュール調整を即座に行えます。
「トラブルが起きてから対応する」のではなく、**“予兆をつかんで先手を打つマネジメント”**が可能になります。
レポート作成・集計業務を自動化できる
工数管理ツールを導入すると、データの集計からレポート作成まで自動化できるようになります。
これまで担当者が数時間かけて行っていた集計やグラフ作成も、ワンクリックで完了。週報・月報のフォーマットも自動で生成できるため、報告作業にかかる時間を大幅に削減できます。
また、ツールによってはダッシュボード機能を備えており、最新データをリアルタイムで共有可能。手作業の集計ミスを防ぎながら、迅速で正確な情報共有を実現します。
業務改善・人件費削減につながる
工数管理ツールを活用することで、業務のムダや非効率を数値で特定できるようになります。「どの業務にどれだけ時間をかけているか」が可視化されることで、不要な会議や重複作業を削減し、作業プロセスの最適化が進みます。
また、業務ごとの時間単価を算出すれば、人件費の適正化やリソース配分の見直しにもつながります。
単にコストを削るのではなく、「本当に価値を生む業務」に時間を再配分できる点が、工数管理ツールの最大の効果です。
経営判断・ガバナンス強化に活用できる
工数データは、現場レベルの改善だけでなく、経営判断の精度を高めるための重要な指標にもなります。プロジェクトごとの採算性や人件費の構造が明確になることで、「どの案件が利益を生んでいるのか」「どこにリソースを集中すべきか」を定量的に判断できます。
また、工数データをもとにしたレポートは、経営層や監査対応にも有効です。業務プロセスと財務の整合性を説明できるため、内部統制(ガバナンス)の強化やIPO準備の信頼性向上にも直結します。
つまり、工数管理ツールは単なる業務効率化ツールではなく、“経営の見える化”を支える基盤なのです。
工数管理ツールの選び方|失敗しないチェックポイント
工数管理ツールは多機能なものが多く、「どれを選べばいいか分からない」と感じる方も少なくありません。しかし、選定時にいくつかのポイントを押さえておくだけで、自社に最適なツールを見極めやすくなります。
ここでは、導入後に「思っていたのと違った」とならないための5つのチェックポイントを紹介します。
目的にあったものを選ぶ
工数管理ツールを選ぶ際にまず重要なのは、「何を目的に導入するのか」を明確にすることです。
たとえば、プロジェクト単位での進捗管理が目的ならガントチャート型のプロジェクト管理対応型ツール、作業時間を正確に把握したいなら工数管理特化型ツール、勤怠や残業時間をまとめて管理したいなら勤怠管理システム搭載型ツールが適しています。
目的が曖昧なまま導入すると、機能を使いこなせなかったり、現場の負担が増える原因にもなります。まずは「自社でどんな課題を解決したいのか」を整理し、その目的に直結する機能を持つツールを選ぶことが成功の第一歩です。
自動計測の有無(入力負担の削減)
工数管理が続かない最大の理由は、**「入力が面倒」**という現場の負担にあります。
そのため、ツールを選ぶ際は、作業ログを自動で取得できる“自動計測型”か、従業員が手動で入力する“手動入力型”かを確認することが重要です。
自動計測型のツールは、PCの操作履歴やアプリ使用時間を自動で記録し、入力の手間をなくしながら正確なデータを蓄積できます。
一方、手動入力型は自由度が高い反面、入力忘れや集計ミスが発生しやすく、運用が定着しにくい傾向があります。現場の負担を減らし、精度の高いデータを長期的に蓄積するには、自動計測に対応したツールを選ぶのが理想的です。
リアルタイム分析のしやすさ
工数データは、**「集めて終わり」ではなく「すぐに活用できる」**ことが大切です。
リアルタイムで集計・可視化できるツールなら、進行中のプロジェクトの課題を早期に発見し、タイムリーにリソース配分やスケジュールの見直しが行えます。
ダッシュボードで稼働状況や進捗を自動更新できる仕組みがあると、報告資料を作る手間も省け、意思決定のスピードが格段に上がります。
特に複数案件を同時に進行するチームでは、**「いまどこに時間がかかっているか」**をリアルタイムで把握できる機能が、プロジェクト成功の鍵になります。
チーム単位での可視化・共有機能
工数管理を組織全体で機能させるには、**「チーム全体で同じデータを見られること」**が欠かせません。個人単位だけでなく、部署・プロジェクト単位で工数を可視化できるツールを選ぶことで、メンバー間の負荷バランスや進捗状況を一目で把握できます。
さらに、チーム全員が同じ指標を共有できれば、「どの業務が遅れているのか」「どの工程に時間を使いすぎているのか」を共通認識として議論でき、改善に向けたアクションが取りやすくなります。
また、共有機能が充実しているツールでは、レポートやダッシュボードを自動で配信でき、マネージャー・現場・経営層が同じ情報をもとに迅速な判断を下せる点も魅力です。
セキュリティ・運用コスト
工数データには、社員の稼働状況や人件費など機密性の高い情報が含まれます。そのため、ツールを選ぶ際には、データの暗号化・アクセス権限の設定・ログ管理といったセキュリティ対策の有無を必ず確認する必要があります。
また、導入コストだけでなく、月額料金・ユーザー数課金・サーバー費用など、運用にかかるトータルコストも比較のポイントです。
特に大規模運用を想定する場合は、料金体系が明確で、将来的な拡張性にも対応できるかを
事前にチェックしておくことが重要です。
導入事例から見る、工数管理ツール活用の成功ポイント
実際にツールを導入した企業が得られた成果を知ることは、自社導入時のヒントになります。ここでは、実際に Qasee(カシー) を活用し、工数管理を改善した企業2社の事例を紹介します。
その中で浮かび上がる「初期運用で重視すべきポイント」「現場が継続できる仕組み」の共通パターンを抽出し、成功に欠かせないポイントとして整理していきます。
導入初期は「入力を減らす」ことを重視する
工数管理を導入した直後に最もつまずきやすいのが、「入力の手間」です。どれだけ高機能なツールでも、現場の負担が増えてしまえば、運用は長続きしません。
そのため、導入初期はまず「正確なデータを取る」よりも、“無理なく続けられる仕組み”をつくることを優先するのがポイントです。
近年は、PC作業ログを自動で取得し、従業員の手入力をほとんど必要としないツールも増えています。このようなツールを活用すれば、記録漏れや入力ミスを防ぎながら、現場の心理的ハードルを下げることができます。
また、初期設定の段階では「どの単位で工数を取るか」「どの業務を対象にするか」を絞り込み、最小限のカテゴリから始めることも大切です。運用が安定してから徐々に粒度を細かくしていくことで、ムリなく精度を高めることができます。
現場と管理者が同じデータを見て改善を回す
工数管理の目的は、データを“集める”ことではなく、データをもとに改善を回すことにあります。そのためには、現場・管理者・経営層が同じデータをリアルタイムで共有できる仕組みを整えることが重要です。
従来は、現場が手動で報告した数字をもとに上長が集計し、経営層に報告する──というように、情報が分断されがちでした。
しかしクラウド型の工数管理ツールを導入すれば、現場の入力や自動計測データがダッシュボードに即時反映され、誰でも同じ情報を閲覧できます。
これにより、管理者は「どこにボトルネックがあるか」「誰に負荷が集中しているか」を早期に把握でき、現場はデータに基づいた改善提案を出しやすくなります。
感覚的なやりとりではなく、“事実ベースの対話”が生まれることで、組織全体の納得感やスピード感も向上します。
定期的なレビュー・フィードバックを仕組み化する
工数データは、集めただけでは意味がありません。重要なのは、定期的に振り返り、改善につなげるサイクルを回すことです。
たとえば、週次・月次でチームごとの工数データをレビューし、「どの業務に時間がかかっているか」「どの工程が非効率なのか」を共有します。
そのうえで改善案を出し合い、次の期間でその効果を検証する――この流れを仕組みとして定着させることが大切です。
また、レビューの場は単なる数字の確認ではなく、現場の声を吸い上げる対話の場にすることもポイントです。データに現れない課題や工夫を共有し合うことで、数値と現場感の両面から改善を促進できます。
このサイクルを続けることで、工数管理は「負担の仕組み」から「成長の仕組み」へと進化します。一度の改善で終わらせず、継続的に見直す文化を育てることが、工数管理を成功に導く最大の鍵です。
業務可視化によって、システム改修効果を“データで測定”できるようにしたイープラスの事例
株式会社イープラスでは、業務システムの改修を重ねながら業務効率化を進めていたものの、「どれほど効果があったのか」を客観的に測定できないという課題を抱えていました。そこで導入されたのが、PC作業ログを自動で可視化できるQasee(カシー)です。
導入の決め手は、UIの見やすさと“監視ではなく改善”を目的とした分析特化設計。導入後は、「リスクアセスメント」や「チームレポート」機能を活用し、アプリ利用率やBiz量(入力量)を起点に業務状況を定量的に把握できるようになりました。
その結果、チャットチャンネルの整理や業務配分の最適化が進み、社員一人ひとりが自身の働き方を振り返る意識も向上。感覚的なマネジメントから、データを基盤とした継続的な業務改善へと移行するきっかけとなりました。
→お客様インタビュー「Qasee導入により実現させた業務の可視化と改善」
可視化で“支援の質”を高めたダンディライオン社の事例
障がい者雇用支援を行うダンディライオン社では、就労後の定着支援を目的に、企業と働く本人をつなぐサポートを行っています。しかし、各企業・案件ごとに「どんな支援にどれだけの時間を費やしているか」が感覚的にしか把握できず、企業からも「サポート内容が見えにくい」という課題を抱えていました。
こうした中で同社が導入したのが、業務の実態を自動で可視化できる「Qasee(カシー)」です。
導入時は「仕分け作業の負担が増えるのでは」と懸念がありましたが、Qaseeの自動仕分け機能によって1ヶ月も経たないうちに運用が定着。メンバーの負担を増やすことなく、プロジェクト単位・企業単位での工数把握が実現しました。
可視化されたデータによって、どの業務に時間がかかっているのか、どの案件で人的リソースが多く必要かが明確になり、サービス内容のブラッシュアップや価格見直しの指標としても活用されています。
また、データをもとに営業資料を作成したり、将来的には採用計画にも活かす構想が進むなど、「感覚」ではなく「根拠」に基づくマネジメントが可能になりました。
→お客様インタビュー「Qasee工数管理で実現した案件ごとのプロジェクト管理」
Qaseeが実現する“自動化された工数管理”
多くの企業が「工数管理の重要性は理解しているが、運用が続かない」と感じています。最大の理由は、**“人の手に頼った記録”**にあります。Qasee(カシー)はこの課題を根本から解決し、自動で工数を可視化・分析できる唯一のプラットフォームです。
PC上の作業ログを自動で収集・分類することで、従来のような「記録の手間」「入力ミス」「集計作業」をすべて排除。誰が・どの業務に・どれだけ時間を使っているかをリアルタイムで可視化し、 “正確で続けられる工数管理”を実現します。ここからは、Qaseeが実現する「自動化された工数管理」の仕組みを、4つのポイントで解説します。
PC作業を自動で可視化し、工数を正確に算出
QaseeはPC上での操作ログを自動的に取得し、誰が・いつ・どの業務に・どれだけの時間を使ったかを正確に算出します。従業員が手入力を行う必要はなく、アプリやWebサイトの使用状況から実際の稼働内容をリアルタイムで可視化します。
これにより、「作業を思い出しながら入力する」「集計が合わない」といった人為的な誤差を排除。常に正確な工数データをもとにした意思決定が可能になります。また、カテゴリ別・プロジェクト別・個人別に分析できるため、ムダな業務の特定やリソース配分の最適化にも直結します。
現場の負担を減らしながら精度を高める仕組み
工数管理が続かない最大の理由は「記録の手間」です。Qaseeではこの負担をゼロに近づけ、 **“入力しない工数管理”**を実現しています。
PC操作ログから業務アプリやWebサイトの利用状況を自動で分類・計測。現場はいつも通りの業務を行うだけで、正確なデータが蓄積されます。さらにAIが作業傾向を分析し、集中度の高い時間帯や業務重複などの改善ポイントを提示します。
記録を減らして精度を上げる──それがQaseeの最大の強みです。
リアルタイムでプロジェクト別・個人別の稼働を把握
Qaseeでは、収集されたデータがダッシュボードに即時反映され、プロジェクト・チーム・個人単位で稼働状況をリアルタイムに確認できます。
これにより、「誰に負荷が集中しているのか」「どのタスクが遅延要因か」をその場で把握し、リソース再配分やスケジュール調整を即時に行うことが可能です。また、個人ごとの業務バランスを客観的に評価できるため、マネジメントや人材育成にも活用されています。
導入企業が実感する成果
Qaseeを導入した企業では、入力作業の手間が減っただけでなく、業務改善のスピードと生産性が大幅に向上しています。
たとえば、ある開発会社では工数入力の作業時間を約80%削減。同時に、レポート作成や稼働集計にかかる時間も月20時間以上短縮されました。
さらに、見える化されたデータをもとに会議の質が高まり、「感覚的な判断」から「データに基づく意思決定」へと移行できたことが大きな成果です。
まずは「見える化」から始めてみませんか
工数管理の理想は、組織全体がデータをもとに改善を続けること。しかし、最初から完璧を目指す必要はありません。
Qaseeなら、PCの操作ログをもとに業務を自動で可視化できるため、導入直後から「どの業務に時間を使っているのか」「何がボトルネックか」を把握できます。まずは“現状を見える化すること”が、継続的な改善の第一歩です。
まとめ|工数管理ツールは“継続できる仕組み”で選ぶ
工数管理の目的は、単に「作業時間を記録すること」ではありません。業務の実態を見える化し、改善を継続できる仕組みをつくることが本質です。
正確なデータをもとに、どの業務に時間がかかっているのかを把握できれば、ムリ・ムダ・ムラを減らし、チーム全体の生産性を高めることができます。そしてその改善サイクルを止めずに回し続けることで、企業全体の成長スピードも確実に上がっていきます。
ただし、どれだけ優れたツールでも「続かなければ意味がありません」。入力が煩雑だったり、現場に負担をかける仕組みでは、運用が長続きせず形骸化してしまいます。
その点、Qasee(カシー)のように自動で工数を可視化できるツールであれば、現場の手間を最小限に抑えながら、正確なデータを日常的に蓄積できます。
「入力しなくても続けられる」仕組みこそ、工数管理を“負担の仕組み”から“成果を生む仕組み”に変える鍵です。
ツール選定のゴールは、導入することではなく、改善が続く文化を根づかせること。
まずは“見える化”から始めて、継続できる仕組みを整えることが、文化を築く最初のアクションです。